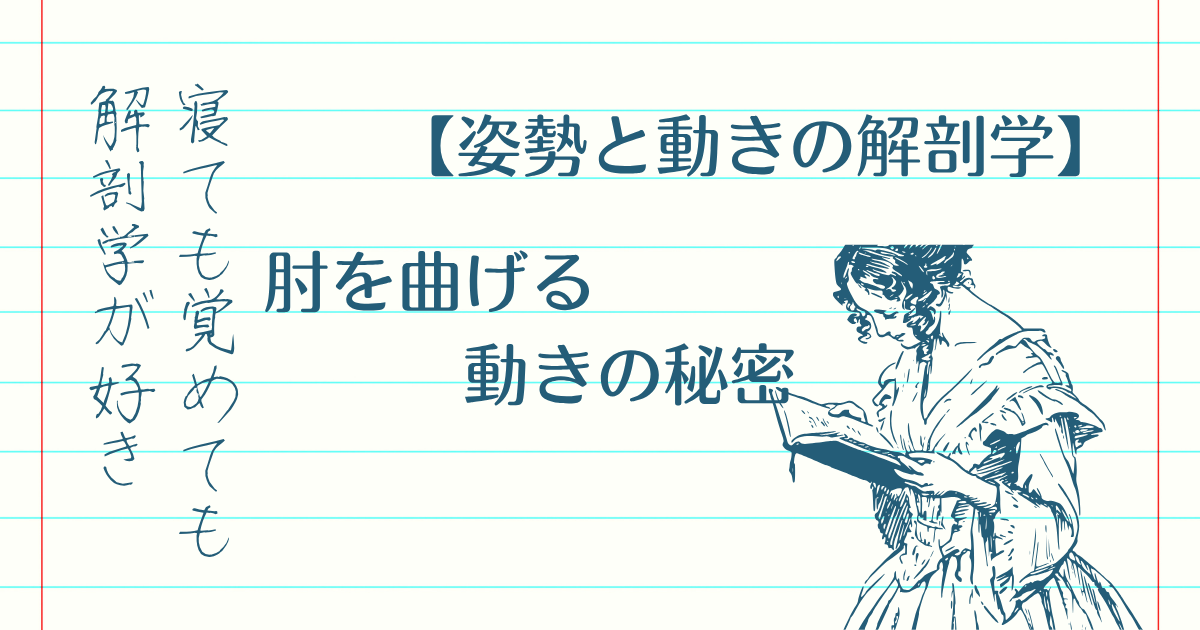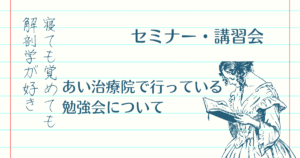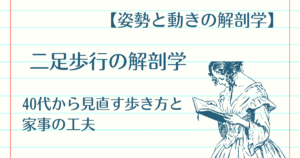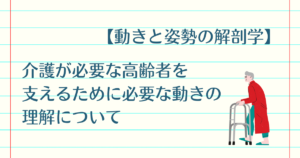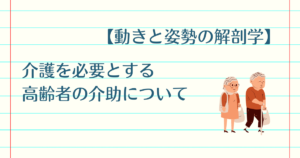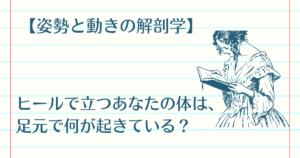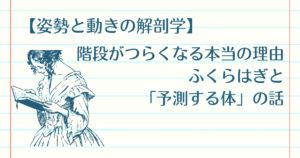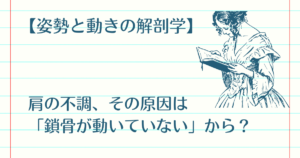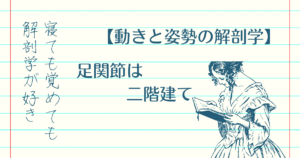ヒトが二足歩行をするようになってから、それまでは前脚として使っていたところ(腕)が自由になりました。
自由になった腕を使うことで火をおこしたりモノを作ったりすることができるようになりました。それがヒトがほかの動物とは異なる特徴のひとつです。
そして、腕を自由に使えることで生活が便利になっただけでなく、文化が発達してより豊かに生きられるのが現代です。
足は移動のために使い、手は文化を培ってきたと私は感じています。
モノづくりに限らず、手や腕を使うことで自由に表現ができる。ダンスなどの身体表現はもちろん、華道や茶道なども器用に使える腕や手指があってこそできる技です。
茶道における臂(肘)
茶道をしている方であれば「利休百首」を知っていると思います。
お茶の心得を百人一首のように表しています。
そのうちの一首に次の歌があります。
茶を振るは 手先をふると思ふなよ
臂(ひじ)よりふれよ それが秘事なり
意味としては、【お茶を点てるときに振る茶筅を手先だけで動かすと力が入ってしまい上手く点てられなくなるので、「肘」全体を使って振ると指先の力は最小限になり美味しいお茶が点てられる、という意味合いです。
「臂(ひじ)よりふれよそれが秘事なり」
一見、ダジャレのように読んでしまいます。しかし、肘の痛みがあるクライアントさんの話を聞いていて思い当たることがあったので、今回はそのことについて綴ります。
いつもの肘の使い方
私たちが日常生活で肘を曲げるのは、どんな時でしょうか。
カバンを持つとき、洋服を着るとき、高いところにあるものを取ろうとする時など、いくつもの場面で無意識に肘を曲げています。
しかし、社交ダンスを踊るとき、お茶を点てる作法のときは意識して肘を曲げて使います。
師匠の動きを見て真似をする段階では、動きの本質はまだ曖昧です。
しかし、自分自身で試行錯誤するなかで気がついた肘の使い方は、日常生活にも活かすことができます。

アームカールの過ち
治療院にお越しになったクライアントさんは、ジムで体を鍛えることを趣味にしていました。
健康のため、体重管理のために筋トレをするのは決して悪いことではありません。
しかし、そのクライアントさんはある時を境に右肘の痛みを訴え始めました。そして施術をすると楽になるものの、なかなかスッキリと痛みが消えない状況が続いていました。

例えば、ダンベルを持って肘を曲げる場面を想像してみます。
写真のように、脇を締めて二の腕(上腕)を体幹にピタッとくっつけて安定させます。そして、肘を曲げながら握ったダンベルを持ちあげます。
いわゆるアームカールという動きです。
これは上腕筋、上腕二頭筋をおもに鍛えるための筋トレです。この動きを運動学の視点で捉えると【ダンベルを持ちあげる前腕が動くためには、上腕を固定させなければならない】と考えます。
たしかにその通りなのですが、日常生活に当てはめると不自然な点が浮かび上がってきます。
荷物を持つように肘を曲げる
果たして、アームカールのような動きは、日常生活でも行われているのでしょうか。
試しにダンベルを持ちあげる筋トレのように、モノを持ち上げる動作で上腕を固定して前腕を曲げるだけの動きをしてみました。
写真では、ダンベルの代わりにスーツケースを持ち上げています。
このような動きでは上腕の筋肉(上腕二頭筋、上腕筋)のみに負担が掛かります。

いかにも筋トレしてます、って感じに見えませんか。斜め上に持ち上げているのか分かります。
果たして、普段もこのような動きをしているでしょうか?
スーツケースを自然に持つときの姿勢は下の写真のようになります。
肘が曲がると同時に、肘を背中よりも後ろに引いています。
このとき、スーツケースは重力に沿って真上に持ち上げられています。

解剖学の言葉で表すと、肘関節の屈曲に加えて肩関節の伸展(肘を引く動き)が同時に行われています。
つまり、日常的な動きでは、上腕二頭筋と上腕筋の動きだけでモノを持ち上げているのではないことが分かります。
このときには肩甲骨まわりの筋肉も働いて、肘と肩の関節が連動して動いていることに気付きます。
ひとつの提案として、アームカールをするのであれば前腕-上腕-肩甲骨を連動させることで肘の故障が少なくなる可能性があります。
今回の投稿は一つの症例のため、体の使い方は一人ひとりのクセがあります。
より詳しい体の使い方については専門家にお尋ねください。